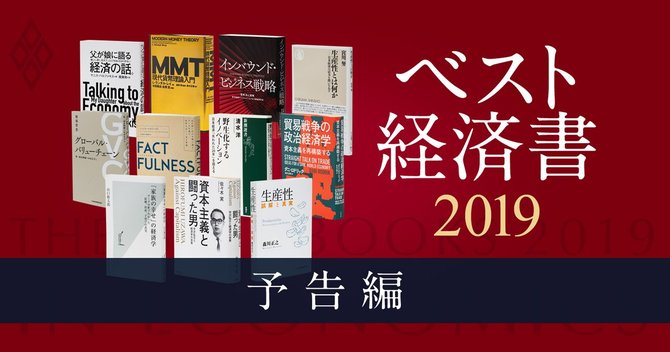
経済学者や経営学者、エコノミスト107人が選んだ2019年の「ベスト経済書」をランキング形式でお届けする「ベスト経済書2019」(全4回)。厳選した良書を、選者による解説付きでお届けする。全10冊の中身をざっくり理解する「ブックガイド」として使うもよし、書籍のおすすめリストとして使うもよし。大人の教養を身に付けよう。(ダイヤモンド編集部編集委員 竹田孝洋)
エビデンス(科学的根拠)に基づく本が
ベスト経済書の上位にランクイン
2019年のベスト経済書ランキングの顔触れを見ると、ここ数年と同様に19年もエビデンス(科学的根拠)に基づく事実を提示する本が上位に入った。政策決定や企業の意思決定の場で、データ分析によるエビデンスに基づき判断することが重要視される流れはますます強まっている。この傾向は続きそうだ。
一方、19年の特徴としては、MMT(現代貨幣理論)など既存の経済学とは違う経済学の在り方を示した本が入ったことが挙げられる。
では、ベスト経済書ランキングに目を移そう。栄えある1位は、山口慎太郎・東京大学教授の『「家族の幸せ」の経済学』。結婚、出産、育児などに関するさまざまな固定観念の間違いを実証研究の結果に基づいて指摘している。
例えば、「赤ちゃんには母乳が一番」という俗説は広く信じられている。しかし、これは必ずしも正しくない。本書では、母乳で育った子供が短期的には健康面や知能面において粉ミルクで育った子供より優位にあることを示す一方で、子供が16歳になった時点ではそうした優位性がなくなっていることを説明している。
3位の経済産業研究所副所長である森川正之氏が著した『生産性 誤解と真実』も、研究結果に基づいて生産性に対する誤解を解いている。働き方改革についてよく聞くのが「労働時間短縮で生産性が上がる」というものだ。本書は、労働時間短縮で一定時間当たりの生産数量や付加価値が増える、つまり生産性が向上するということの論拠は乏しいことを説いている。
このほか、5位のハンス・ロスリング氏らによる『FACTFULNESS』もデータに基づき、われわれが常識と考えていることの誤りを指摘してくれる書である。
次なる19年のキーワードは既存の主流派経済学への批判だろう。
既存の経済学とは違う経済学の在り方を示した書として、まず挙げられるのが2位の佐々木実氏の『資本主義と闘った男 宇沢弘文と経済学の世界』。本書では、希代の経済学者、宇沢弘文氏が米国での名声を捨て日本に帰国し、主流派経済学に対抗し、資本主義が引き起こす問題を捉える理論を構築する中で思想を紡いでいった過程が描かれている。
19年に注目を集めたMMT。L・ランダル・レイ・米バード大学教授の『MMT現代貨幣理論入門』が8位だ。通貨発行権を持つ自国通貨建ての政府債務は増大しても不履行にはならないというのがこの理論の要旨。財政赤字が膨らめばインフレなどの弊害が生じるという主流派経済学の考えとは相反するものである。
2019年『べスト経済書』ランキング ベスト10
Key Visual designed by Kaoru Kurata
"ベスト" - Google ニュース
December 27, 2019 at 03:15AM
https://ift.tt/2SrbzTF
「ベスト経済書2019」トップ10!学者・エコノミストら107人が厳選 - ダイヤモンド・オンライン
"ベスト" - Google ニュース
https://ift.tt/2qhuftC
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini














0 Response to "「ベスト経済書2019」トップ10!学者・エコノミストら107人が厳選 - ダイヤモンド・オンライン"
Post a Comment